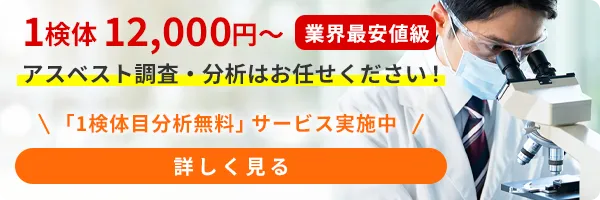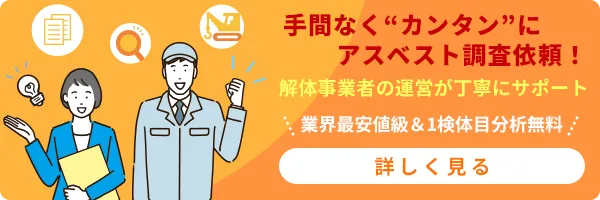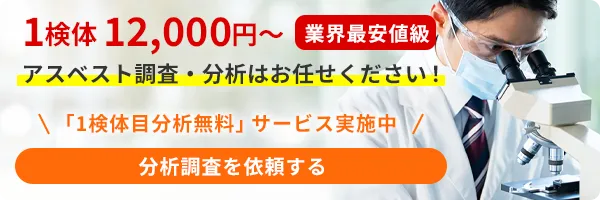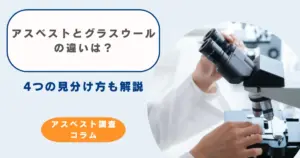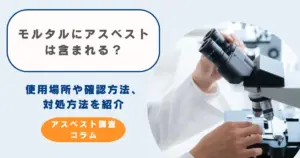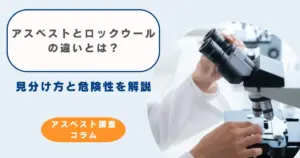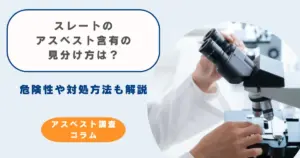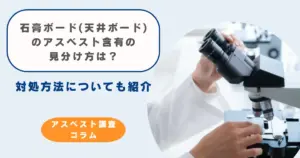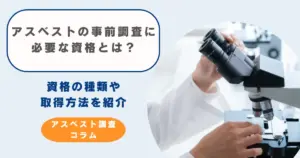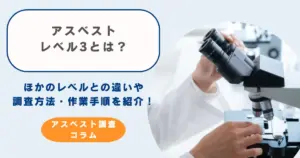アスベスト(石綿)は、非常に細かい繊維でありながら、高い耐火性と断熱性、耐久性を持つため、古くから建築資材や工業製品に広く利用されてきました。
しかし、飛散したアスベストの微細な繊維を吸い込むことにより、肺がんや中皮腫、石綿肺などのリスクがあることが明らかになり、1975年から規制が始まりました。
さらに2005年には、旧クボタの工場で従業員やその家族、周辺住民にまでアスベスト関連の疾患が多発している事実がわかり、その後段階的な規制強化へとつながっています。
本記事では、アスベスト規制の対象年度を時系列に沿って解説します。
【この記事で分かること】
・アスベスト規制の歴史
・アスベストを含む建物を見分ける方法
・築年数以外にアスベストの有無を見分ける方法
アスベストは何年以降から規制された?
アスベスト規制の歴史は以下の通りです。
- 1975年(昭和50年)|アスベスト含有率5%を超える建材の使用禁止
- 1995年(平成7年)|アスベスト含有率1%を超える建材の使用禁止と規制対象の追加
- 1995年(平成7年)|アスベスト含有率1%を超える建材の使用禁止と規制対象の追加
- 2004年(平成16年)|規制対象の追加
- 2006年(平成18年)|アスベスト含有率0.1%を超える建材の使用禁止
- 2012年(平成24年)|猶予措置の撤廃
各年代ごとに、詳しく見ていきましょう。
1975年(昭和50年)|アスベスト含有率5%を超える建材の使用禁止
1975年10月1日に特定化学物質等障害予防規則が改正され、アスベスト含有率が重量の5%を超える場合は、吹き付け作業への使用が禁止されました。ただし、5%未満の場合は、特に制限がありません。
この改正は、主にアスベストへのばく露防止対策を中心とした内容であり、アスベスト製品の製造等の禁止といった強い規制措置が取られていません。
そのため、この時期に建築された建物は、吹き付け材を中心にアスベストが含まれている可能性が高いです。
1995年(平成7年)|アスベスト含有率1%を超える建材の使用禁止と規制対象の追加
1995年4月1日、特定化学物質障害予防規則と労働安全衛生法の2つが改正されました。特定化学物質等障害予防規則の改正により、アスベストの含有率基準が5%から1%に変更されています。
具体的な内容は下記のとおりです。
■特定化学物質等の障害予防規則の改正(一部抜粋)
別表第一(第二条、第二条の二、第五条、第十二条の二、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第三十六条、第三十八条の四、第三十八条の七、第三十九条関係)
一 アクリルアミドを含有する製剤その他の物。ただし、アクリルアミドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二 アクリロニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、アクリロニトリルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三 アルキル水銀化合物を含有する製剤その他の物。ただし、アルキル水銀化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三の二 インジウム化合物を含有する製剤その他の物。ただし、インジウム化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三の三 エチルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、エチルベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
引用:特定化学物質障害予防規則 別表第1|労働法検索|労働新聞社
さらに労働安全衛生法では施行令の改正により、規制の対象が追加されました。これにより、屋根材、床材、外壁材などで使用されていたアモサイト(茶石綿)やクロシドライト(青石綿)の製造、輸入、使用が全面禁止となっています。
労働安全衛生法の改正内容の詳細については、次のとおりとなります。
■労働安全衛生法の改正(一部抜粋)
一 第一六条関係
石綿のうちアモサイト及びクロシドライトは、他の種類の石綿に比べて発がん性が著しく強く、人体に与える影響が大きいこと、また、昭和六一年にILOにおいて採択された「石綿の使用における安全に関する条約(第一六二号条約)」においてクロシドライトの使用禁止が求められ、平成元年に開催されたWHOの専門家会議においてアモサイト及びクロシドライトの使用禁止が求められていることから、これら二物質を製造等が禁止される有害物(以下「製造等禁止物質」という。)に追加したものであること。
三 第二二条関係
アモサイト及びクロシドライトが製造等禁止物質に追加されたことに伴い、特定業務に従事していた労働者に対する健康診断の対象となる有害物として、新たに、これら二物質を追加するとともに、併せて第二項第八号の「石綿」からこれら二物質を除くこととしたものであること。
引用:・労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則及び特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令の施行について(◆平成07年02月20日基発第76号)
また、労働安全衛生規則により、吹き付けアスベスト除去作業には事前の届け出が義務化されました。
2004年(平成16年)|規制対象の追加
2004年10月1日の労働安全衛生法施行令改正により、アスベストを1%以上含むとされる10品目の製造などが禁止されました。
■労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行について(一部抜粋)
(1) 石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)には、クリソタイル(白石綿)、アンソフィライト、トレモライト及びアクチノライトが含まれること。
(2) 石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)をその重量の1%を超えて含有する石綿セメント円筒等の製造等が禁止されるものであり、すべての石綿セメント円筒等の製造等が禁止されるものではないことに留意すること。
なお、石綿セメント円筒等以外の石綿を含有する製品については、従前のとおりとすること。
引用:・労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行について(◆平成15年10月30日基発第1030007号)
労働安全衛生法施行令改正によって新たに対象になった品目は、以下のとおりです。
- 石綿セメント円筒
- 押出成形セメント板
- 住宅屋根用化粧スレート
- 繊維強化セメント板
- 窯業系サイディング
- クラッチフェーシング
- クラッチライニング
- ブレーキパッド
- ブレーキライニング
- 接着剤
2006年(平成18年)|アスベスト含有率0.1%を超える建材の使用禁止
2006年9月1日の労働安全衛生法施行令改正により、次のようにアスベストの含有率基準が0.1%に引き下げられました。これにより、アスベストが原則使用できなくなりました。
具体的な改正内容は次のとおりです。
■政令関係(一部抜粋)
(1) 平成18年9月1日以降、別添に掲げる物を除き、石綿を含有するすべての物の製造、輸入、譲渡、提供又は使用(以下「製造等」という。)を禁止すること。
また、平成18年9月1日前に製造され、又は輸入された建材、シール材等のいわゆる在庫品についても譲渡(販売)することはできず、また、使用することもできないこと。
なお、同日において現に使用されている物について、同日以後引き続き使用されている間は、製造等の禁止の規定は適用されないが、これを改修等により新たな物に交換する場合には、石綿を含有しない代替物とする必要があること。
(2) 規制の対象となる「石綿を含有する製剤その他の物」について、石綿をその重量の「1%を超えて含有するもの」から「0.1%を超えて含有するもの」としたこと。
引用:労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の周知について|厚生労働省
ただし、代替が難しい一部の製品(ガスケットやパッキン等)においては、条件付きで猶予措置がとられています。
2012年(平成24年)|猶予措置の撤廃
2012年3月1日には、以下のように猶予措置がとられていたアスベスト含有製品もすべて使用禁止となりました。これにより、新たに建設される建築物や設備などにアスベストが使用されることはなくなりました。
■労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令の周知について(一部抜粋)
厚生労働省としては、適用除外製品等についても、早期の代替化を促進して
きたところですが、今般、最後の品目についても代替化が可能となったことか
ら、労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成24年政令第13号。
以下「改正令」という。)により平成 18 年一部改正令の改正を行い、これらの
製造等を禁止しました。
引用:労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令の周知について
アスベストの事前調査の義務化については下記の記事で解説しています。こちらもあわせてご覧ください。

アスベストを含む建物の築年数に関してよくある質問
ここでは、アスベストを含む建物の築年数に関するよくある質問とその解答を紹介します。
2006年以降の建物ならアスベストは含まれていない?
法改正は2006年9月1日に施行されましたが、それ以前に着工した建物であれば、アスベストが使用されている可能性があります。2006年に着工した建物は、9月1日以降かどうかも確認しておくと安心です。
また、9月1日以降は事前調査での実地調査が原則不要ですが、設計図書や契約書、登記簿などでアスベストの不使用を証明できない場合、事前調査が必要になる場合があります。
鉄筋コンクリートの建物でも築年数が古いとアスベストが含まれている?
2006年までに建てられた鉄筋コンクリートの建築物は、防音・断熱目的でアスベストが含まれている可能性があります。
コンクリートの中でも、鉄筋コンクリートではなくセメント、砂、砂利、水のみで構成された純粋なコンクリートであれば、原則アスベスト調査が不要とされています。
しかし、コンクリートにアスベストが含まれているか見分けるのは非常に困難です。特にコンクリートは、アスベストとほかの素材と混ぜ合わせて使用するため、見た目だけでは判断がつきません。
そのためアスベストの有無を調べる場合は、専門家による調査が必要です。
アスベスト事前調査が不要な築年数は?
着工日が2006年9月1日以降で、設計図書等で着工年など確認がとれる場合は、書面での調査を行ったとみなされ、目視での調査は不要とされています。
ただし、設計図書などに記載がない場合や、増改築がなされている場合は「建築物石綿含有建材調査者」の資格保持者による、現地での目視調査が必要なケースもあります。
また、事前調査が不要なケースでも、アスベスト使用の有無に関しての結果を労働基準監督署等へ報告する義務はあるため、調査結果の記録作成と3年間の保管が必要です。
築年数以外にアスベストを見分ける方法
築年数以外にアスベストを見分ける最も確実な方法は、解体業者や工務店が連携しているアスベスト会社に依頼することです。色で見分ける方法や、酢を吹きかける、触るといった方法でも確かめられますが、安全上おすすめできません。
アスベストの詳しい見分け方は下記記事で紹介しています。あわせて参考にしてみてください。
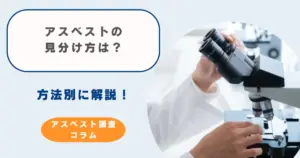
まとめ
アスベストの使用は、1975年以降から段階的に規制され、2006年以降は原則禁止されています。2006年9月1日以降の建築物であれば、アスベストが使用されていませんが、築年数のみでアスベストの有無を判断することは難しいのが実情です。
築20年を超える住宅やマンションのリフォーム、解体を考えている場合は、アスベスト調査の実施が確実です。アスベスト調査を検討中でしたら、ぜひアスベストジャッジにご相談ください。
調査に必要な送付セットはこちらで用意するため、お客様で用意していただくものはありません。
1検体あたり12,000円+税(3営業日で対応)と、業界最安値級の価格で調査実施いたします。急ぎの検査にも対応しており、即日(1営業日)なら1検体あたり19,800円+税で調査可能です。
分析依頼は電話・メールで承っております。調査にかかる無駄な手間が省けるよう、現場に合ったやり方もご提案できますので、ぜひご検討ください。